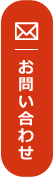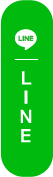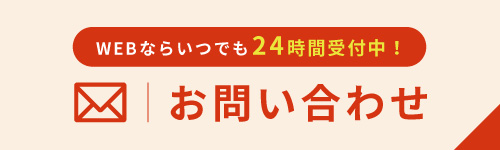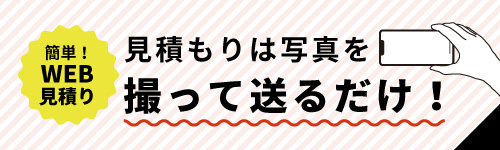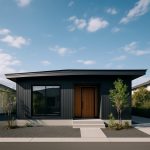お家に無くてはならない照明*おしゃれな内玄関を演出する照明の選び方とは?おすすめ照明器具もご紹介
こんにちは☀京都市・伏見区でリフォーム、リノベーションをお考えの方はハウスウィンドウへお気軽にご連絡ください☎
今年の夏も猛暑が続いていますね!
あまり出歩かず涼しい場所で過ごして熱中症にならないよう気をつけましょう!
さて、今回は玄関照明について家族や身内専用の玄関である「内玄関」は、店舗やオフィス、規模が大きい戸建て住宅などで
見られるものでしたが、最近では急な来客があっても慌てずに済むようにと、
一般的な広さの戸建て住宅でも「ファミリー玄関」という形で採用されるケースが増えています。
そこで今回は、内玄関に適した照明の選び方についてご紹介します。
内玄関におすすめの照明器具についても事例を交えながら解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
内玄関の照明の選び方
内玄関の照明を選ぶ際は、「明るさ感・色温度・照明の高さ」の3つのポイントを押さえておく必要があります。
では、それぞれの選び方のポイントについて、詳しく見ていきましょう。
内玄関照明の選び方①:明るさ感について
内玄関の広さに適した照明の明るさ感を知るための予備知識として、
最初に「ワット(W)」と「ルーメン(lm)」について解説します。
電気屋さんに電球を買いに行くと、「60形」といった表記がされていますが、これは「60W相当の明るさ」という意味になります。
厳密に言うと、ワット(W)とは明るさの単位ではなく消費電力の単位であり、消費電力が高いほど明るく、
反対に低いほど暗くなっていきます。
しかし、白熱電球よりも熱エネルギーの消費が抑えられるLED電球が登場したことで、
これまで目安としていたワット数と明るさ感がかみ合わなくなりました。
そこで新たに、光源から放出される光の量(光束)を表す単位である「ルーメン(lm)」が登場します。
ワット数と同様に、数値が高いほど明るさ感が強くなり、低いほど暗くなります。
ただ、実際のところルーメン表記だと白熱電球との比較が難しいため、
家庭向けのLED照明には「○形相当」という表記がされていることがほとんどです。
例えば、「60形相当」とは「白熱電球で言うと60ワット相当の明るさ」という意味になります。
本題に戻りますが、内玄関は2〜3畳・天井高240〜250cmが平均的な広さとなっており、
白熱電球であれば60W(40〜60形)、LED電球であれば810〜1,160lmで十分な明るさが確保できます。
これ以上の明るさになると夜の帰宅時にとても眩しく感じ、逆に暗くなると靴を履き違えてしまう可能性があるでしょう。
●3畳以下:40〜60W(40〜60形)/485〜810lm
●4〜6畳:80〜100W(80〜100形)/1,160lm~1,520lm
内玄関照明の選び方②:色温度について
色温度とは光源が発する光の色のことで、数値が低くなるほどオレンジがかった光になり、
高くなるほど青みがかった光になります。また、色温度は「ケルビン(K)」という単位で表します。
| 色温度の種類 | JISの相関色温度範囲 | 代表的な色温度 |
|---|---|---|
| 電球色 | 2600〜3,250K | 2,800K |
| 温白色 | 3,250〜3,800K | 3,500K |
| 白色 | 3,800〜4,500K | 4,200K |
| 昼白色 | 4,600〜5,500K | 5,000K |
| 昼光色 | 5,700〜7,100K | 6,500K |
一般的におしゃれな空間と感じやすいのは電球色ですが、内玄関では靴を着脱するほかにも、全身鏡で身だしなみを整えたり、
郵送物の内容を確認したりといった作業が発生しますので、色味や文字の判別に適した昼白色や昼光色が適していると言えるでしょう。
特に、色の識別が難しい方や、視力が悪い方が利用される空間であれば、コントラストが強まる昼光色がおすすめです。
内玄関照明の選び方③:照明の高さについて
内玄関の照明選びで大切な要素の3つ目が、照明の高さについてです。
一般的な内玄関の天井高は240〜250cmとなっており、
この場合、上がり框の真上付近に60W相当の主照明を設置するとちょうど良い明るさ感が確保できます。
構造上どうしても内玄関が吹き抜けになってしまう場合や、あえて吹き抜けにして開放感を持たせたいといった場合は、
天井からの照明だけでは床面まで光が届かないことがあるため、シャンデリアやペンダントライトで照明位置を低くしたり、
補助照明としてスタンドライトや間接照明を組み合わせるなどで、明るさ感を補う必要があります。
また、照明の高さについては、空間の縦の長さだけでなく、横の長さも考慮しなければいけません。
この時に必要となる要素が配光です。
配光とは、光源や照明器具から、どの方向に対して、どの程度の光の強さが出ているかを示すものです。
配光には、ほぼ全ての範囲を照らす全方向タイプと、半円状に照らす広配光タイプ、
手元や足元といった一部の範囲を照らす下配光タイプがあります。
また、同じ配光タイプでも電球や照明器具によって光の広がり方が異なります。
もともと内玄関はそこまで広い空間ではなく、設置できる照明器具の数が限られますので、
一つの照明器具で全体を明るく照らすことが可能な全方向や広配光の照明器具が適していると言えます。
内玄関におすすめの照明器具
内玄関は家族や従業員が使うところですので、お客様用の表玄関ほど見栄えにこだわる必要はないものの、
外出時は気持ち良く、帰宅時はホッとするような居心地の良い空間にしたいところです。
また、お気に入りの写真やアイテムを飾る方も多いでしょう。
このような実際に空間を使うシーンを想定しながら、内玄関におすすめの照明器具についてご紹介していきます。

ダウンライト
ダウンライトとは、天井に埋め込む小型の照明器具です。主に上がり框のちょうど上辺りに設置して、内玄関全体を照らします。
ダウンライトには、配光角度が狭いものから幅が広いタイプまでありますので、空間の大きさに応じて選ぶと良いでしょう。
ダウンライトのメリットは、あらかじめ造作に埋め込んであるため、空間がスッキリする点です。
一方で、天井が高い空間だと足元まで光が届かないことがあるため、
上がり框やシューズボックスの下に間接照明をプラスするなどの対策が必要になります。
また、内玄関から廊下が続く場合も、1灯だけでは明るさが十分に確保できません。
この場合、2畳あたり1灯を目安に複数配置していくと良いでしょう。
シーリングライト
シーリングライトとは、天井に据え付ける照明器具です。上がり框の真上や、空間の中央付近の天井に配置します。
シーリングライトのメリットですが、基本的に配光タイプが全方向・広配光となっていますので、
1灯だけで内玄関全体に一様の明るさが確保できます。
そのため、広めの内玄関や、十分に明るさ感を確保したいという場合に適していると言えるでしょう。
デメリットとしては、意匠性に欠ける点があげられます。例えば、光を天井や壁面に反射させて空間を照らす間接照明は、
反射面の造作によって陰影が生まれ、空間に奥行き感や立体感を演出します。
その点、シーリングライトは天井から直接空間を照らしますので、単調な印象になりがちです。
このような理由から、おしゃれな空間を楽しみたい方には不向きな照明器具ですが、
視力が悪い方・小さな子供・ご高齢の方が使用する内玄関におすすめです。
ペンダントライト/シャンデリア

ちょうど視界に入る床上210〜250cm程度の高さに配置すると良いでしょう。
デメリットとしては、高い物を運ぶ際や、子供が何かを投げて遊んでいる際に、ぶつけてしまう可能性がある点です。
破損によってケガをする恐れがありますので、割れやすいガラス製のものを避けるなどして対策する必要があるでしょう。
間接照明

間接照明とは、天井・壁・床といった造作に光を当てて、拡散された光で空間を間接的に照らす照明のことです。
間接照明を内玄関に採用するメリットとして、空間がおしゃれになる点と、目への刺激が抑えられる点があげられます。
一方デメリットとしては、空間全体を均一に照らすことが難しく、明るい場所と暗い場所ができてしまう点です。
そのため、内玄関で間接照明を使用する際は、
他の照明器具や照明手法と組み合わせて空間に必要な明るさ感を確保する必要があります。
例えば、天井に反射させるコーブ照明や、壁に反射させるコーニス照明、写真やインテリアアイテムを際立たせる棚照明、
間接照明と同じく造作の中に光源を埋め込むダウンライトなどが代表的な組み合わせ例となります。
内玄関の照明選びで悩んだら……
今回は、内玄関に適した照明の選び方と、おすすめの照明器具をご紹介しました。
ダウンライトやシーリングライトなどの自身でメンテナンス可能な照明であれば、
後から気軽に明るさや色味を変えることができますが、
シャンデリアや間接照明のような取り付けに専門知識が必要な照明の場合は、最初のプランニングが重要となります。
なかでも間接照明は造作に光源を隠す必要があるため、建物そのものを設計すると同時に、
照明プランについても検討しなければなりません。照明器具はメーカーによっても見え方や明るさに差がありますので、
建築士や空間プランナーだけでは対応が難しい場合があり、「思っていたのと違った」と後悔する方が少なくないのです。
このような失敗を避けたい方や、照明にこだわった空間を作りたいという方は、照明の専門家を加えて設計を進めると安心でしょう。
******************************************
お客様の「家」への想いをカタチに京都でリフォーム、リノベーションならハウスウィンドウにお任せください。